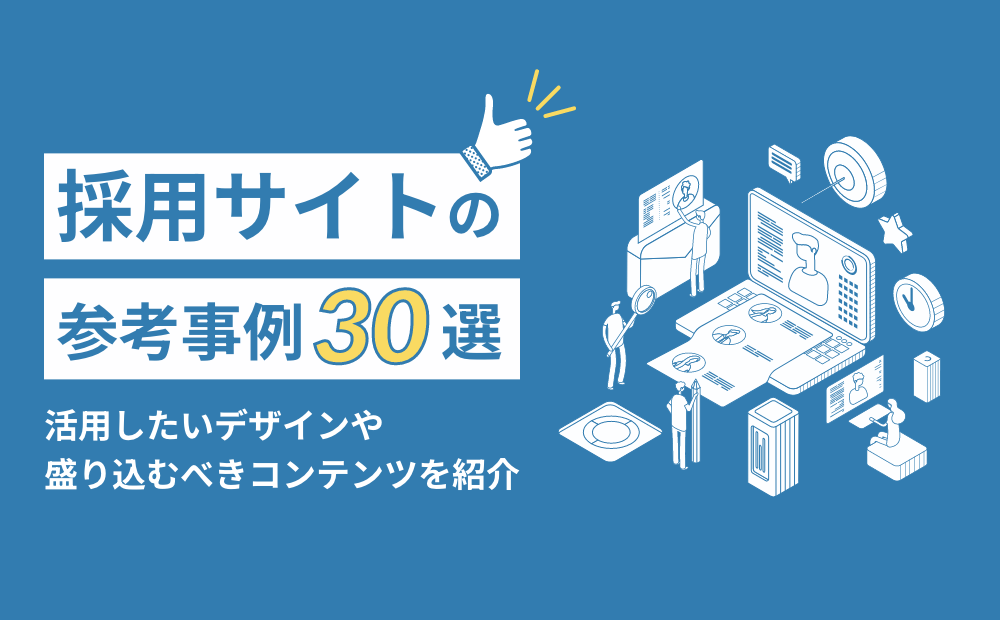失敗しない採用サイトの作り方|構成設計・コンテンツ例・費用相場まで解説

「採用サイトを作りたいけど、何から始めればいいのかわからない…」そんな悩みを抱える採用担当の方は、実はとても多いですよね。
求人サイトや媒体だけでは、自社の魅力をすべて伝えきれない——。
そんな課題を解決する手段として、以前から注目されているのが「採用サイト」です。
会社の雰囲気や働く人の声、カルチャーなど、求職者が本当に知りたい情報を、わかりやすく、そして魅力的に伝えられるのが強みです。
とはいえ、いざ作るとなると、「どんな手順で進めるの?」「外注と内製、どっちがいいの?」など、考えることがたくさんありますよね。
この記事では、Webサイト制作のプロの視点から、採用サイトづくりの流れを一つひとつ丁寧に解説していきます。
情報の整理方法からデザインのコツ、運用のヒントまで、すぐに役立つ実践的な内容をギュッとまとめました。
採用力アップの第一歩として、ぜひ参考にしてみてください!
目次
採用サイトの必要性と効果を知る
「採用サイトって、本当に必要なのかな?」と迷っている方も多いと思います。
たしかに、企業サイトや求人媒体を使えば、ある程度の採用活動は可能です。
でも、それだけで「本当に来てほしい人」に届いているかというと、そうとは限りません。
採用サイトには、ほかの採用手段では伝えきれない魅力を、しっかり届ける力があります。
この章では、採用サイトの役割や他チャネルとの違い、ブランディングやコスト面でのメリットなどを整理しながら、「なぜ必要なのか」を具体的に掘り下げていきます。
応募数の増加やミスマッチ防止の理由
採用サイトには、「ただ応募者を集める」だけでなく、「自社に合う人と出会いやすくなる」という効果があります。
その理由は、事前に社風や働く環境、将来のキャリア像などを丁寧に伝えることで、求職者の中での“働くイメージ”がはっきりしてくるからです。
現場で働く社員の声や、リアルなオフィスの写真があるだけで、「自分がここで働く姿」を想像しやすくなります。
その結果、選考途中の辞退や、入社後のミスマッチによる早期離職を防ぐことにもつながります。
採用ブランディングに必要な理由
採用サイトは、自社の「らしさ」をしっかり伝えるための、ブランディングツールとしても活躍します。
たとえば、「挑戦を歓迎する社風」や「女性が活躍できる職場」「地域に根ざした価値観」など、文章だけでは伝わりにくいニュアンスも、写真やデザインで表現することができます。
そうした想いや雰囲気に共感してくれた人が応募してくれることで、入社後の定着率も高くなる傾向があります。
さらに、ブランディングがしっかりできていれば、求人媒体を使わなくても「この会社で働きたい」と思ってもらえる可能性が高まり、直接応募の導線もつくれます。
長い目で見れば、採用サイトは“採用力”を支える大切な資産になるのです。
採用ブランディングの考え方や文化づくりとの関係については、こちらの記事も参考になります。

コーポレートサイトや求人広告との違い
採用サイトは、コーポレートサイトや求人広告とは目的も伝える内容も大きく異なる情報発信のメディアです。
まず、コーポレートサイトは、主に顧客や取引先、株主などを対象に、経営方針や事業内容を伝えることで、企業全体の信頼性を高めることを目的としています。
一方で、求人広告は、短期間でできるだけ多くの応募者を集めるための手段。
募集職種や給与など、必要最低限の情報をコンパクトに伝えることが重視されており、掲載期間が限られているのも特徴です。
それに対して、採用サイトは、自社の魅力を“じっくり・しっかり”伝えるための場です。
社風や働く環境、社員の声、価値観など、求人広告では伝えきれない情報を多角的に発信することで、「この会社で働きたい」と思ってもらえる関係づくりを目指します。
応募者をただ増やすだけでなく、自社のカルチャーに共感し、長く活躍してくれる“マッチした人材”と出会うために。
それこそが、採用サイトのいちばんの目的です。
求人媒体依存を脱却できる仕組み
求人媒体には、掲載期間やレイアウトの制限があるため、自由な情報発信が難しいという側面があります。
その点、採用サイトならコンテンツの構成も表現方法も自由自在。
動画や写真、インタビューなども組み合わせながら、求職者に響く情報をしっかり届けられます。
特に中小企業やベンチャー企業では、求人媒体の費用負担が大きくなることも。
そんなとき、自社メディアとしての採用サイトを育てていくことで、コストを抑えつつ、継続的に人材を集められる体制を作ることができます。
さらに、Google検索やSNSとの連携を意識した設計にすれば、自然な流入を増やすことも可能。
採用サイトを形にするための基本設計
採用サイトは見た目だけでなく、情報の整理や全体構成、デザイン、さらには制作体制にいたるまで、しっかりと設計することが成功の土台になります。
まずは、訪れる人にとって見やすく伝わりやすいサイトをつくるための基本から見ていきましょう。
情報の整理とサイト構成のポイント
採用サイトの構成を考えるとき、「伝えたいことを全部載せる」だけでは、うまくいきません。
大切なのは、求職者の立場に立って「どの情報が、どこにあれば見やすいか」を考えることです。
理想は、サイトマップ(全体の構成図)を先に作って、情報を目的ごとに分けたシンプルな階層にすること。
さらに、スマホからの閲覧も多いため、スクロールしやすさやボタンの配置にも配慮して設計するのがポイントです。
採用サイトのデザイン成功例と落とし穴
見た目の印象は、サイトの第一印象を大きく左右します。
成功例としてよく挙げられるのが、「企業の雰囲気」や「社員の表情」が一目で伝わるファーストビューを持つデザインです。
ただし、デザインにこだわりすぎて動きが多すぎたり、操作が複雑になったりすると、かえって逆効果になることもあります。
大切なのは、「誰に、どんな想いを届けたいか」を明確にして、そのメッセージに合ったデザインを選ぶこと。
内製と外注、それぞれの判断ポイント
採用サイトの作り方には、大きく分けて「内製」と「外注」の2つがあります。
社内にWeb制作のスキルがあり、時間にも余裕があれば、自社で制作することでコストを抑えることも可能です。
無料で使える「採用サイト作成ツール」などを活用すれば、予算をかけずにスタートすることもできます。
一方で、「初めての制作で何から手をつけたらいいかわからない」「ブランディングまでしっかり考えたい」といった場合には、制作会社に依頼するという選択肢もあります。
外注する場合の費用は、内容によって異なりますが、一般的に50万円〜300万円ほどかかることが多いです。
参考までに、費用感の目安は以下のとおりです。
- テンプレート利用:10〜50万円程度
- オリジナルデザインの小規模サイトor採用LP:50〜150万円程度
- 自由度の高い更新機能+戦略設計+撮影まで含めたプラン:150~300万円が一般的
判断の基準は、「この方法が、ちゃんと成果につながるかどうか」
目的や体制に合わせて、最適な手段を選ぶことが、失敗しないためのコツです。
求職者に響く採用サイトの作り方
採用サイトの魅力を高めるには、求職者の関心にしっかり寄り添ったコンテンツが欠かせません。
ただ伝えたいことを並べるだけでなく、「どんな情報が響くのか」を意識することで、共感を呼び、応募にもつながりやすくなります。
ここでは、求職者目線で考えるべきポイントを紹介します。
求職者が本当に知りたい情報とは?
採用サイトを考えるとき、まず大事なのは「求職者が何を重視しているか」を知ることです。
マイナビなどの調査では、労働条件や勤務地、キャリアの可能性、そして職場の雰囲気などが、重視される項目としてよく挙げられています。
一方で、企業としてはビジョンや理念を伝えたい気持ちが強くなりがち。
でも、それだけでは求職者の心には届きにくいこともあるのです。
まずは、求職者の目線に立って、「この会社で働いてみたい」と思ってもらえるような情報を優先的に届けることが、応募につながります。
具体的にどんな情報が必要なのか、最新の調査や事例をもとに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考になります。
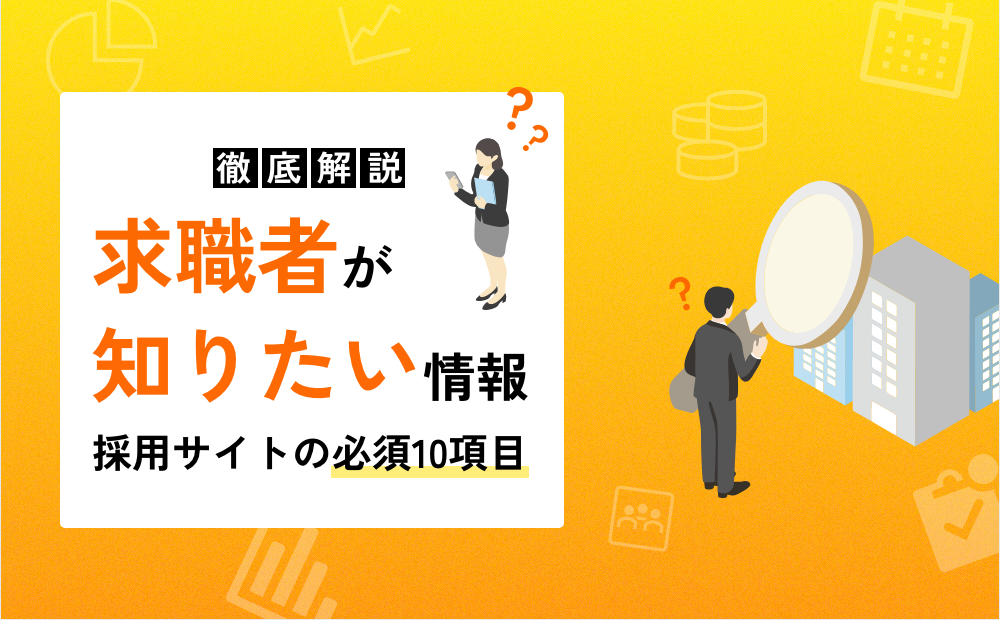
差がつく!職場のリアルを伝える工夫
他社と差をつけるには、職場の“リアルな姿”をどれだけ伝えられるかが大きなポイントです。
抽象的な言葉よりも、写真や動画、社員の一日など、実際の様子が伝わるコンテンツのほうがリアルな魅力が伝わりやすくなります。
会議の様子や、社員同士の雑談風景、働く姿などが見られる動画があれば、「ここで働く自分」を想像しやすくなります。
こうしたリアルな情報は、サイトの中でも目につきやすい場所に配置するのが効果的です。
ファーストビューに取り入れたり、動きを加えたりすることで、自然と目を引き、サイトへの興味や関わりも深まりやすくなります。
職種別LPや属性別構成の活用法
最近では、職種や属性ごとにランディングページ(LP)を分けて情報を届ける構成が注目されています。
たとえば、営業・エンジニア・事務などの職種別、あるいは新卒・中途・女性・育児中といった属性別にページを設けることで、求職者は「自分に関係のある情報」にスムーズにアクセスできます。
特に、専門職やニッチ人材の採用においては、このような的を絞った情報設計が応募の後押しにつながります。
求職者ごとの「共感ポイント」に焦点を当てることで、エントリーの質と数、どちらにも良い影響を与えることができます。
よくある見落としポイントと改善案
採用サイトでは、つい後回しにされがちな情報の中に、実は求職者にとって大切な要素がたくさんあります。
求職者が安心材料として重視するのが、研修やキャリアパス、福利厚生のような情報です。
また、社員ストーリーやよくある質問(FAQ)などの補足情報も、信頼感を高めるうえで重要です。
これらを求職者が「気になったとき」に見られるように配置すれば、サイトからの離脱を防ぐ効果もあります。
“どんなタイミングでどんな情報を届けるか”という視点で設計することで、成果の出る採用サイトに近づきます。
採用サイトの作り方|手順と制作のポイント
採用サイトの制作には、押さえておきたい8つの基本ステップがあります。
ここでは、これまでご紹介してきた内容を踏まえながら、具体的な流れとポイントを整理していきます。
①目的を決める|採用課題を整理し、ゴールを明確にする
まずは、自社が今抱えている採用課題をしっかり洗い出すことから始めましょう。
そのうえで、「どんな採用サイトをつくれば、課題解決につながるか」を考え、目的を明確にしていきます。
たとえば「応募が集まらない」と感じている場合は、企業理念や職場の雰囲気など、“人となり”が伝わるコンテンツを検討してみましょう。
社内のリアルな様子を発信することで、求職者の関心を引きやすくなります。
一方で、「自社に合わない人が多く応募してくる」といったミスマッチに悩んでいるなら、ターゲットをより明確に設定し、その人物像に響く表現やビジュアルを意識することが大切です。
採用サイトの目的とゴールを定めることは、効果的なコンテンツ設計の土台となります。
②ターゲットを決める|求める人材像を具体化する
次に大切なのが、「どんな人に来てほしいか」を明確にすること。
ただ「やる気がある人」「経験がある人」など、抽象的なイメージでは効果的な訴求にはつながりません。
よくあるミス
- 抽象的な人物像になってしまう
- 募集職種のニーズと合っていない
- 理想が高すぎて該当者が極端に少ない
うまくいくターゲット設定のコツ
- 実在の社員や他社の人材を参考にする
- 募集ポジションに必要なスキル・経験を明確にする
- 年齢や収入、転職の動機なども具体的にイメージする
- 性格や価値観、ライフスタイルにも目を向ける
ターゲットがはっきりすれば、自社の魅力をどう伝えるか、どんな言葉が響くのかが自然と見えてきます。
▶︎たとえば、成長意欲のある30代マネージャー層をターゲットにする場合…
響きやすいフレーズ例:
- 「未来を切り拓くポジションをお任せします」
- 「裁量ある仕事で、自分らしく活躍できる環境」
- 「新規事業を立ち上げるリーダーを募集」
- 「プライベートも大切にできる働き方を実現」
上記は一例ですが、自社に合った言葉を選ぶことがとても大切です。
③自社の強みを分析し、魅力を“伝わる言葉”にする
採用サイトの成功には、「自社の強み」をしっかり把握し、それをわかりやすく伝えることが欠かせません。
「どんな仕事ができるのか」「どんな働き方ができるのか」
求職者が“入社後の自分”をイメージできるような表現を意識しましょう。
たとえば、
- 「実力次第で若手にもチャンスがある」
- 「仕事と家庭を両立できる制度が整っている」
- 「チームワークを大切にする温かい社風」
といった、入社後の前向きなイメージにつながるメッセージが効果的です。
こうした言葉で“この会社で働きたい”と感じてもらえるように工夫することが、エントリー数アップのポイントになります。
④サイトに必要なコンテンツを決める|情報設計の準備段階
採用サイトの成功には、どんな情報を、どのように伝えるかをしっかり見極めることが重要です。
この企画段階での判断が、サイトの質や成果を大きく左右します。
ターゲットに「ここで働きたい」と思ってもらえるコンテンツを企画できれば、応募数はもちろん、マッチ度の高い人材からの応募も増えていきます。
採用サイトに掲載する主なコンテンツ
- 募集要項・仕事内容
- 企業紹介・ビジョン・ミッション
- 代表メッセージ
- 社員インタビュー
- 福利厚生・働く環境
- キャリアパスや研修制度
- よくある質問(FAQ)
- オフィス紹介・1日のスケジュールなど
どのコンテンツを選ぶかは、「採用コンセプト」や「ターゲット像」に合わせて、取捨選択することが大切です。
むやみに情報を詰め込むのではなく、伝えるべき内容を明確に絞ることで、より効果的なサイトになります。
自社の魅力がいちばん伝わる構成は何か?という視点で、社内でしっかり議論してみましょう。
⑤サイトマップを作成する|ページ構成の整理と導線設計
コンテンツが固まったら、次はサイトマップ(ページ構成表)を作成しましょう。
サイトマップは、Webサイト全体のページ構成を一覧化したもの。
訪問者が必要な情報に迷わずたどり着けるようにするための、“ナビゲーションの設計図”ともいえます。
サイトマップを作るメリット
- 求職者が知りたい情報をスムーズに見つけられる
- サイト全体の情報の過不足を確認できる
- 将来的な更新や改善にも役立つ
また、採用後の分析や施策検討においても、「どのページがどれだけ見られているか」などのデータを活かすために、整理された構成があると非常に便利です。
⑥コンセプト設計・デザインのポイント|第一印象を決める要素とは?
採用サイトのデザインは、ターゲットに合った雰囲気やメッセージを視覚的に伝えるための大切な要素です。
なかでも、最初に目に入るメインビジュアル(トップの画像やキャッチコピー)は、サイトの第一印象を大きく左右します。
こんな点にこだわってみましょう
- 採用ターゲットが共感できる写真やキャッチコピーを選ぶ
- 企業の個性が伝わるトーン&デザインを採用する
- 応募ボタンの位置や色も工夫し、迷わず行動できるようにする
- スマホでも快適に見られるUI/UX設計にする
「見た目のおしゃれさ」だけに偏らず、“誰に何を伝えたいか”をデザインに落とし込むことが、成果につながる鍵になります。
コンセプトとデザインの方向性が合っていれば、自然と「この会社、なんかいいかも」と思ってもらえるサイトになるはずです。
⑦取材・撮影の進め方|社員の声と社内の雰囲気を“見える化”する
採用サイトづくりで欠かせないのが、社員インタビューや社内風景の写真・動画といった「リアル」が伝わるコンテンツです。
代表のメッセージや働く人たちの表情が見えるだけで、求職者にとっては会社の雰囲気が身近に感じられ、共感や信頼にもつながりやすくなります。
焦らず丁寧に進めることが、満足のいく仕上がりへの近道になります。
撮影を進めるときのポイント
●働く様子やリラックスした瞬間を自然に切り取る
撮影では、社員が実際に働いているシーンや、ふと力が抜けたリラックスした表情など、リアルな日常のひとコマを意識して撮るのがおすすめです。
空っぽのオフィスや、かしこまった集合写真よりも、ありのままの雰囲気が伝わるカットの方が、見る人にも温度感が伝わりやすくなります。
●インタビューでは「話しやすい空気づくり」も大切に
社員インタビューは、原稿の内容だけでなく、どんな雰囲気で話してもらうかも重要なポイントです。
かしこまりすぎず、安心して話せる空気をつくることで、自然な言葉や表情が引き出され、より伝わるインタビューになります。
●仕上がりにこだわるなら、プロへの依頼もひとつの手
写真の構図や光の使い方、インタビューでの質問の仕方ひとつで、コンテンツの印象は大きく変わります。
予算に少し余裕がある場合は、プロのカメラマンやライターにお願いしてみるのもおすすめです。
完成度がぐっと上がり、採用サイト全体の魅力にもつながります。
社員の声や社内の様子をリアルに伝えるコンテンツは、会社の第一印象を決める“顔”のようなものです。
魅力がしっかり伝わる採用サイトにするためにも、こうした表現を大切にしながら、ひとつひとつ丁寧につくり込んでいくことが大切です。
⑧公開後の運用と改善|ATS連携や運用のしくみも忘れずに
採用サイトは「作ったら終わり」ではありません。むしろ大事なのは、その後の運用です。
応募者情報の管理や選考の進捗確認などは、ATS(採用管理システム)と連携することで、格段にスムーズになります。
また、GoogleAnalyticsやヒートマップと連動すれば、「どこで離脱されているか」「どのコンテンツがよく読まれているか」といった分析も可能に。
さらに、更新性の高いCMS(コンテンツ管理システム)を導入すれば、運用担当者でも簡単にコンテンツの修正ができます。
最初から運用を見据えて設計しておくことで、採用サイトは“育てていける資産”になります。
継続的に成果を出していくためにも、運用の仕組みづくりはとても大切です。
採用サイトを作るタイミングはいつがベスト?
採用サイトの効果を最大限に発揮するには、「いつ作り始めるか」「いつ公開するか」がとても重要です。
一般的に、サイトの制作には3〜4ヶ月ほどかかるため、スケジュールには余裕をもって取り組むのがおすすめです。
ここでは、新卒採用・中途採用それぞれに最適な制作&公開タイミングをわかりやすくまとめました。
新卒採用サイトは【9月〜11月】に制作スタート
新卒向けの採用サイトは、就活の情報解禁日である3月1日に公開するのがベストタイミング。
この時期に合わせて公開すれば、学生の目にもとまりやすく、エントリー数にもつながりやすくなります。
サイト制作には3〜4ヶ月かかるため、遅くとも11月には制作を始めるのが理想的。
さらに、ターゲット設定や採用課題の整理など、準備が必要な工程もあるので、9月頃から準備を進めておくと安心です。
中途採用サイトは【転職市場の動き】にあわせて公開を
中途採用では、転職活動が活発になる時期に合わせて公開するのが効果的です。
特に、4月は新年度に向けて転職希望者が増えるタイミング。
この流れに乗るには、2月〜3月にサイトを公開するのが理想です。
そのためには、前の年の8月〜10月に制作をスタートしておくと、スケジュールにも余裕が生まれます。
そのほかにも、1月〜3月・6月・9月〜10月は転職希望者が比較的多い時期。
こうしたタイミングに合わせて公開したい場合も、少なくとも3〜4ヶ月前には制作に取りかかることをおすすめします。
採用サイトは、「いつ作るか」よりも「いつ公開したいか」から逆算して動くのがコツです。
時期を見極めて計画的に進めることで、採用活動のスタートダッシュをスムーズに切ることができます。
よくあるご質問
採用サイトの制作を検討していると、「本当に必要?」「どうやって作ればいいの?」など、いろいろな不安や疑問が出てくるものです。
特に初めての取り組みでは、情報が足りずに一歩を踏み出せないこともありますよね。
ここでは、実際によく寄せられる質問に、できるだけ具体的で現場目線の回答をまとめました。
採用サイトを考える際のヒントや後押しになればうれしいです。
Q.採用サイトって本当に必要なんでしょうか?
A.はい、必要性を感じて導入される企業が増えています。
たしかに、求人媒体だけでもある程度の応募は集まりますが、「情報が少なくて伝わらない」「ミスマッチが多い」といった課題もつきものです。
採用サイトなら、自社の魅力や働くリアルな雰囲気を、写真や動画、社員の声などを通じてしっかり伝えられます。
媒体に頼りきりになっている、コストが気になってきた、応募者の質を高めたい——そんなお悩みがあるなら、採用サイトは中長期的に大きな武器になります。
Q.内容がまだ固まっていないのですが、制作をお願いできますか?
A.もちろん大丈夫です!
むしろ「何から考えたらいいかわからない」という段階から相談できる制作会社も多くあります。
採用の目的整理や、どんな人に来てほしいか(=ターゲット像)の言語化なども、プロの視点で一緒に進められるので、結果的に内容の抜けやブレを防げます。
方向性がまだ曖昧だからこそ、早めに外部の力を借りて整理していくのがおすすめです。
Q.制作期間はどれくらい見ておくべきですか?
A.制作内容によって前後しますが、一般的には1.5〜3ヶ月ほどを目安に考えておくとよいでしょう。
構成の設計、原稿のライティング、デザインやコーディング、写真や動画の撮影など、複数の工程が関わるため、社内の確認フローも含めて、あらかじめスケジュールを立てておくことが大切です。
もし「できるだけ早く公開したい」といった緊急性がある場合は、テンプレートを活用したスピード制作プランなども選択肢になります。
目的やリソースに応じて、柔軟に検討してみてください。
Q.採用サイトの制作費用はいくらくらいかかりますか?
A.無料で使える「採用サイト作成ツール」もありますが、制作会社に依頼する場合は、一般的に50万円〜300万円ほどかかることが多いです。
費用は、テンプレートを使った簡易なものから、オリジナルデザイン・撮影・戦略設計まで含めた本格的なプランまで、内容によって大きく変わります。
自社の採用課題や目的に合わせて、予算と相談しながら検討するとよいでしょう。
Q.小規模な会社でも、採用サイトって意味ありますか?
A.実は、小規模な企業こそ採用サイトが効果を発揮しやすいです。
大手企業が多く掲載されている求人媒体では、ネームバリューで埋もれてしまうことも…。
でも採用サイトなら、自分たちらしい魅力をしっかり伝えることができます。
たとえば、代表の想いや、社員同士の距離感、地域に根ざした働き方など、小さな会社だからこその温かさや誠実さが、求職者の心に届きやすくなります。
Q.写真や動画などの素材がないと作れませんか?
A.ご安心ください。素材がなくても、テキストベースで進めることは可能です。
また、制作会社によっては撮影サービスも提供しています。社員インタビューやオフィスの風景など、プロが撮影すればより自然でリアルな魅力が伝わります。
もちろん、無理のないスケジュールで準備を進めればOK。
最初はテキスト中心で公開し、あとから素材を追加していく方法もありますよ。
Q.公開後の運用や改善がうまくできるか不安です
A.採用サイトは「公開して終わり」ではなく、「公開してからがスタート」です。
GoogleAnalyticsやヒートマップを活用すれば、「どのページで離脱が多いか」「どの情報がよく読まれているか」などがわかり、改善に活かせます。
また、CMS(更新管理システム)を使えば、採用情報の修正や社員の紹介追加なども、社内で簡単に対応できるようになります。
制作会社によっては、運用サポートまで引き受けてくれることもあるので、事前に確認しておくと安心です。
「改善しながら育てていく」という考え方で取り組むのが、成功する採用サイト運用のコツです。
まとめ
ここまで、採用サイトの必要性や掲載すべき情報、作り方のステップや外注の判断ポイントまで、段階を追って整理してきました。
なかでも特に大切なのは、「誰に向けて」「どんな価値を届けたいのか」をしっかり見据えること。
その軸があるだけで、構成やデザイン、コンテンツの方向性がぶれずに進められます。
求人媒体だけに頼る採用から一歩抜け出して、もっと“自分たちらしさ”が伝わる採用を目指すために。
採用サイトは、自社の魅力をしっかり届けるための、非常に頼もしい手段になります。
「何から始めればいいか不安」「自社でうまく作れるか自信がない」
そんな時こそ、どうぞお気軽にご相談ください。
戦略の設計からサイトの具体的な制作まで、私たちが伴走しながら、理想の採用を一緒に形にしていきます。
採用サイト制作
Pick up
ピックアップ記事

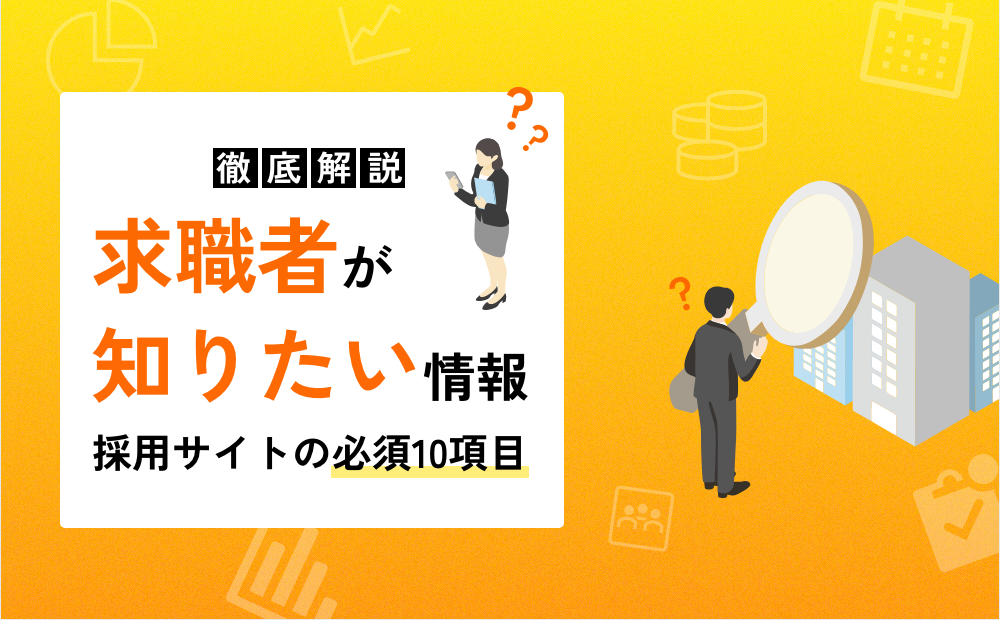

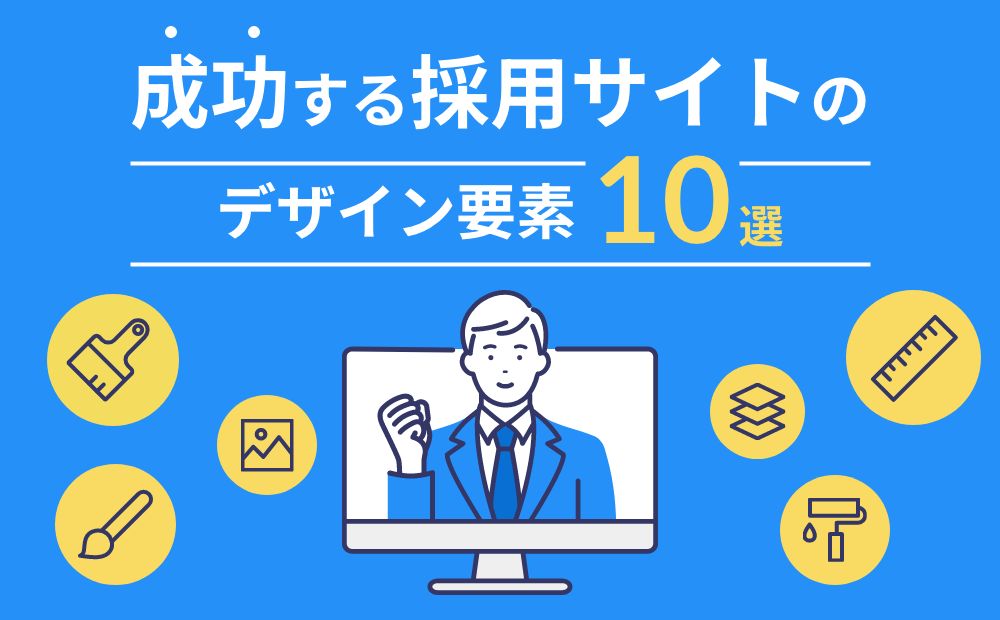
Key word
人気のキーワード